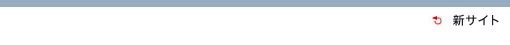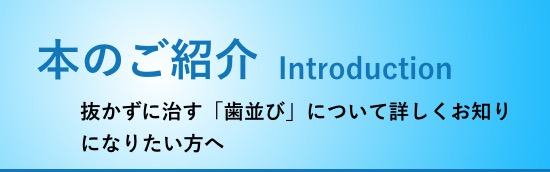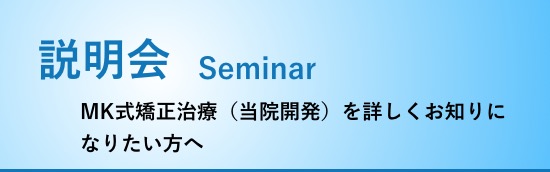歯は重要な臓器
歯を抜かない矯正治療を行なう私に対し、つぎのようなたとえ話を持ち出す矯正歯科医がいます。
「6人がけのベンチがあります。ここに8人来たら、どうしますか?」
当然、ベンチに腰掛けられない人が2人出てきますから、その2人にはご遠慮いただくしかありません。歯も同じで、6本しか入らないスペ−スに8本あれば、入らない2本を抜く、こういう論法です。
6人がけのベンチに8人の人がいれば、腰掛けられない人が2人出てくる。ここまでは当然の話で、私にも異論はありません。しかし、その先はまったく違います。口が小さいから、スペ−スがないから、入らない歯を抜いてもいいなど、とんでもない話です。
なぜかといえば、ベンチは物体であって、人数以上の人が腰掛けようとしても無理ですが、口は物体ではないからです。口は消化器官という立派な臓器です。臓器は、大きくなったり小さくなったり、状況に合わせて柔軟に形を変えられる性質をもっています。
同じ消化器官である胃を例にとれば、よくおわかりのことと思います。ふだんはご飯を一膳しか食べない人がいるとします。ところが、大好きなステ−キが食卓に並ぶと、ご飯をお代わりしたりします。もし胃が同じ容量しか入らない物体なら、ご飯も一膳しか入らないずです。
しかし、胃はそのときの状況に応じて、大きく小さくなったりできるのです。 心臓にしても同じです。小さいときからマラソンをしている子供は、心臓がきたえられて少しずつ大きくなっていきます。しかし、だらといってその分肺臓が小さくなることはありません。肺も同じ大きさと機能を保って共存しています。臓器はその環境に適応しながら共生しており、それが生きている臓器というものなのです。
口や歯も同じです。臓器ですから状況に合わせて柔軟に対応できますし、使っているうちにきたえられ、大きくなっていきます。ここが、大きさが決まっていて、容量に限度のある物体と根本的に違う点です。
小臼歯を抜いてもいいと考えている歯科医は、口や歯や顎を物体と見ているのではないでしょうか。歯科の世界では、石膏の模型を使って患者さんの歯並びを考えます。石膏はベンチと同じように物体にすぎません。だから、そこから飛び出した歯は入りません。
しかし、患者さんの体を直接見て、生体としてとらえるなら、そういう発想にはならないはずです。人間は生きていて、常に変化し、環境に適応しながら生存しているのです。
歯の1本1本は、生命体に必要なものとして備わっています。それは進化論や生物の発生学、人間咬合学などを学べばわかることです。ですから、健康な歯を安易に抜いていいわけがありません。歯を抜かなくても、歯の大きさと口腔のバランスを取れば、いまある口の中にピタリとおさまるはずです。それを可能にするのが、私たち矯正医の技術であり、仕事だと思います。